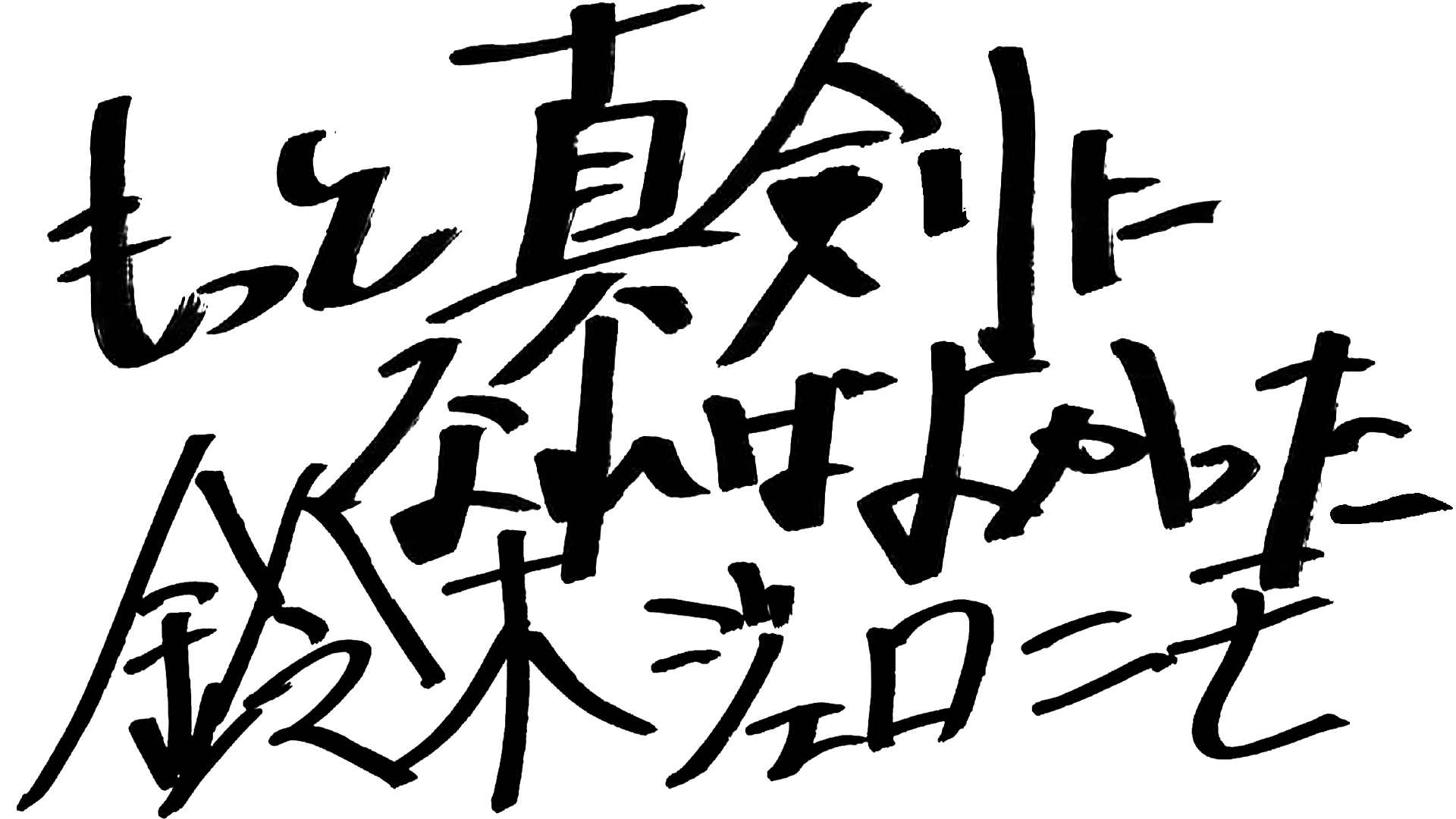ドアノブを掴んでドアを開ける。中学生になったことをきっかけにできた自分の部屋。ドアの先はその空間になっていて空気の動きが他とちがう。ない大きなプロペラが回っているようなリビングの空気でもなく、雪が降りてくるような廊下の空気でもない、自分の部屋の、布製の風船を膨らませている途中の60%から70%にかけて、みたいな空気。それがまだ電気をつけて明るくなる前の空間に滞在している。自分の部屋に入ることは安心感のあるホームに帰るというよりも、外の世界に比較的順応しやすそうな「自分の部屋」と呼ばれるものがあって一旦そこに体を置く、という感覚に近い。周りが自分を自分の名前で呼んでいるからその名前が自分の名前なのだと自覚していくように、自分が自分の部屋に何度も入るからそこを自分の部屋と思っていく。他の空間と比べて相対的にそこにあるものたちがある程度私に従おうとしてくれている。そういう信頼を少しずつ知っていくことで、その空間を自分の部屋だと思うことと言うことのずれが軽減されていく。
ドアを開けて2秒は経った。まだ電気をつけていない。ドアを開ける前から暗さのなかがずっと気になっている。携帯電話がちいさく光らないか待っている。でもそれを待っているということを携帯電話に知られたくなくて、あくまでも電気をつける動きがゆっくりになっているだけですよと、電気のスイッチの方にまず意識をゆっくりと、次に手をゆっくりと動かすことにする。今はその途中。
携帯電話はまだ光らない。メールが来ていた場合、二つ折りになった携帯電話の中心あたりにあるライトが光ることになっている。ゆっくりだけれど点いて消えてを繰り返すから一応点滅ということになっているその光は、眠っているときに名前を呼ばれて慌てて返事をしたような、一度の光の後ろの方に最大光量があってその直前は返事が漏れ出たような、瞬間的なじわわっとした光り方をする。暗い部屋の中でまだ光らない携帯電話のライト。それをああ、自分がドアを開ける寸前に一度光ったからその次の点灯までの最も長いインターバルが今で、そこにたまたま自分が同席しているんだな、と思う。本当は携帯電話にメールが届いていて、それを知らせるために光るはずなのだけれど、たまたま今が、光と光の間なんだな、と私の中で結論づく。
結論づけて、まだ光らない。そのあたりでようやく堪忍して、メールが来ていないんだ、と理解する。しかしそれはおかしい。本当というのは私の中ですでに完成している物語の方で、その物語に則るとすればメールは来ているはずなのだ。自分の部屋が存在しているこの現実というものが、私の完成させた物語に則っていない。自分の部屋は自分の部屋なのだけれど、それは自分ではない。自分であればメールは来ているのだから。そういう思いの末に、依然として暗いままの自分の部屋を、自分の管轄にないものだと諦める。自分ではない自分の部屋を過剰に期待しない対象の一つとして認定する。
4秒は経っただろうか。そこでようやく電気の、電気と呼んでいるけれど適切な言い方をすれば照明の、スイッチを押す。パパラパパン、パパラン……。小さすぎてほとんど音とも言えないような音と共に、照明が起動する。部屋の天井の中心に取り付けられた、その空間の中でたった一つの丸い照明が、空間をあおじろく確定させる。それまでの暗闇の中では壁と壁の繋ぎめは緩やかなカーブを描いていたような、そうあって欲しいと最小の期待を込めていたような気がするけれど、明るさが確定させた壁の繋ぎ目は直角だった。窓と勉強机に挟まれてそこにしか居場所がないと肩を窄めておとなしくしている私のベッド。ベッドの上に掛け布団。掛け布団の中心からやや枕寄りの位置に、柔らかさがとぷんとへこんだ点がある。そこに携帯電話がある。自分の部屋を出たさっきの自分がそう置いた。二つ折りの中心部分の点滅ライトが見えるように、その部分が布団ではなく空間に向かって上向きに置いてある。やはりライトは光らない。光らない携帯電話に最初から期待していなかった方の自分を呼び出す。まあそうだよね、というかいや別に、何が?とその自分は言う。もう一度照明を消してドアを閉める。リビングに行って夕食を食べる。
中学生の後半で携帯電話を持ち始めた。高校受験のために電車に乗って塾に通わせてもらうことになり、その送り迎えの連絡のため、という必要性が出て持たせてもらうことになった。中学生時代の私は流されるは易き、其れ即ち弱き、のような頑固思想でありながら表面ではのらりくらりを気取っていたので、携帯電話を持たせてもらえることは嬉しかったはずなのに、その嬉しい自分を許せなかった。ケータイ? ああまあじゃあ一応持ちますけど、ハイ。みたいな不遜ゆえに今思い返すと愛おしい態度をとっていた。だから最新版をねだればいいのに、そういう自分への許せなさが王位を譲らなかったためいわゆる「らくらくホン」を買ってもらうに至った。電話とメールだけができる。丸みのある二つ折りの板にうっすらボタンがついている。メールの文字が大きくて7文字くらいで改行されてしまう。その不格好さが自分らしくておもしろかった。みんなのようになりたいのではなく自分らしくなりたかった。
絵文字のことを感情の強制と呼んでいた。絵文字で示される感情はあなたが勝手にそうなっているだけで私には関係ないですよね、その感情になってくださいと言われても困ります、といった具合に嫌悪を示していた。「!」と「〜」を駆使していかにモノクロなままでメール本文を書き切るかに熱心だった。しかし何人かと何通かのメールをやり取りする中で、意味がないな、と思ってこだわるのをやめた。反発としてこだわることは自然ではないと思った。友達から送られてくるメールの絵文字に触れて、犬の絵文字は犬という情報だけを示すのではなく、その表情の犬が存在する空間からメールが届いたかのようなあたたかさを私に伝えようとしているんだ、と気づいたときに嬉しかった。絵文字は感情の強制でも情報伝達でもない、どちらかといえばBGMや装飾のような、そこに書かれた言葉のスピード調節を目的としたものなのだと友達に遅れて理解した。
光っている。夕食を食べ終えてやはり期待しない方の自分が開けたドアの先の暗い空間の中に、携帯電話が光っている。水色と緑の中間のような、その二色がほとんど同時にしかし順番に光ったような色。暗い空間の中の、さっきの自分がそこに置いたと確信のある位置の携帯電話の光。ということはベッドの大きさはこのくらいか、とそれ以外のもののサイズを無意識のうちに逆算する。押したら光る、そう信頼している照明のスイッチに手を伸ばしながら携帯電話の光をまだ見ていたい気持ちになって、照明のスイッチを触る寸前で手が止まる。するともう一度、暗い空間に自分の携帯電話が光る。それは規則的な時間を経てまた光る。メールが来ている。そのことが奇跡のように嬉しい。花火の最中の夜空に太陽が急いでやってくることがないように、このメール通知を示す光をしばらく光らせたい。ぱわっ…ぱわっ…ぱわっ…。もう光ると知った光が等間隔にずっと光る。蛍を嬉しがったことはないけれど蛍もこのくらい嬉しいのだろうか。
あんまりずっと光らせておくと急かされているような気持ちになって来て、はいはいはい、と照明のスイッチを押す。部屋が味気なく明るくなる。掛け布団の上に丁寧な気持ちでわざと雑に置いた携帯電話が、明るくなった部屋の明るさに遠慮してちいさく光る。馴染みのある甲虫のように手のひらで掴んで、二つ折りの間に指を差し入れるようにして、内側からの指の力を使ってひらく。画面の中にメールを知らせることが書いてある。想像上の腹筋のように位置取られたボタンたちを押して操作し、新着メールに辿り着く。
はるです!
しょーごからメアド聞いたよ〜(目)
よろしくね(顔)
()の部分は絵文字。(目)は二つの目がキョロっと何かを発見したような様子。(顔)はピンク色で描かれた、両目をつぶって安らぎの中で笑っているような顔。今の環境ではここに記入することが叶わないiモードの絵文字たち。好きかは分からないけれど愛してはいた友達をこれから好きになるかもしれなかった。