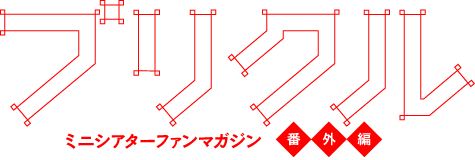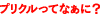20090709
7月9日(木)
『パンドラの匣』
山道をバスが走っていく。たらいに注がれた水が主人公の顔を、短く刈った頭を濡らす。ただそんな冒頭のいくつかの場面を見ただけで、これから始まるこの映画にすっかりひきこまれてしまうだろうことを予感する(車が走っているのに何も感じさせない映画なんて面白いはずがないのだ)。
バスには川上未映子演じる竹さんが乗っている。薄いが横に広い、紅の引きがいのある唇だ。竹さんは看護婦長として赴任する結核の療養所「健康道場」に向かっている。
そこは木造2階建の小さな建物。まるで理科室の机のような、いわゆる病院のベッドより高さのある一風変わった寝台が前後3つずつ並んでいる部屋で、主人公のひばり(染谷将太)は療養生活を送っている。前列の一番奥の窓際がひばりの場所。道場の日課は、不思議な呼吸法や、助手と呼ばれる看護婦の女の子たちが、肺病者たちの背中をごしごしとブラシのようなものでこすったり、はちみつかなにかとろりとしたものを舌の上にのせてやったり、突き出されたおでこに指で軟膏をひょいとつけたりと、どきりとする身体接触がちりばめられているのだが、蝶々のようにひらひらと舞う看護婦たちと彼らのふれあいは、彼女たちの白いふわりの制服のように清潔で、甘酸っぱい青春の香りをいたずらに越えることはしない。死と隣り合わせの現実も、「やっとるか」「やっとるぞ」「がんばれよ」「ようしきた」という冗談めいた合言葉が軽やかにぬぐってくれる。
ひばりの部屋はおそらく1階で、ときどき2階に上がって窓辺に腰をかけ下で洗濯物を干す助手のマー坊を見下ろしたりしているのだが、そこから遠くに望めるであろう風景は一度も出てこない。遠く、といえば上方の空のみだ。それほど閉じた空間が舞台であるはずなのに、不思議と閉塞感を意識させないのはなぜか。太陽をたっぷり浴びたみかんのようなマー坊の存在ゆえか。ちょっとした秘密が露呈する人目を避けた階段や布団室も、彼女はなんだか明るく照らしてしまう可憐さなのだ。
会話はたぶん全篇アフレコで微妙なズレがあり、時には声が二重になったりして水の中の出来事を見ているようでもあり、浮世から離れた場所での物語であることを後押しする。そうした一風変わった手法が主張しすぎることなく物語と伴走している。玉音放送とともに喀血したひばりは「あたらしい男」を目指していると度々口にし、手紙に書いてもいるのだが、そんなひばりを描くのに、こうした目新しい方法がマッチしたのかもしれない。
ひばりの恋心は揺れている。夜明け前の庭に裸足で出て行きうろついて戻ってくると、やはりそんな時間に起きだしていた竹さんに遭遇する。月の光に照らされた台所で、ひばりは汚れた足を差し出す。竹さんの持つ濡れた手ぬぐいの感触が、はっきりと残る印象的なシーンだ。結局、竹さんは来るときと同じように憂鬱な面持ちでバスに乗り、道場を去ってゆく。彼女とバスだけが移動する。一方、残された囚われの人たちの、生命感に満ちた楽しそうな幕切れ。その爽やかさ。
それにしても、本当は何より、ひばり=染谷将太(『14歳』でも『フレフレ少女』でも、彼は抜群に光っていた!)の透明な眼が忘れられないのだ。
(大嶺洋子)
『パンドラの匣』
監督・脚本・編集:冨永昌敬、出演:染谷将太、川上未映子、仲里依紗、窪塚洋介、洞口依子、ミッキー・カーチス他、原作:太宰治『パンドラの匣』、配給:東京テアトル、10月、テアトル新宿ほか全国順次ロードショー